
出産した方にお祝いを渡す時に悩んだことありませんか?
この書き方で失礼ではないかな…?大丈夫かな?と不安になりますよね。
意外と多くの方が悩んでいる書き方やマナー。
そこで今回は、「出産祝いの書き方・マナー」についてまとめていきます。
出産祝いの書き方は?

出産祝いの袋を祝儀袋と言いますが、最近ではあらかじめ「出産祝い」と書かれている祝儀袋が多く販売されています。
このあらかじめ書かれている祝儀袋を購入した場合は、差出人の名前を下の部分に記入すると完成です。
何も書かれていない袋を購入した場合は、上の部分に「出産祝い」「御出産祝」と縦に書き、下の部分には差出人の名前を記入しましょう。
中袋にも書き方がある?

祝儀袋によって違いますが中にもう1つ袋が入っている祝儀袋もありますね。
この祝儀袋の中に入っている袋を中袋と言います。
あまり意識しない方もいるのですが、実は中袋にも書き方のマナーがあります。
まっさらな中袋は、漢数字で包む金額を記入します。
1万円を包む場合「金壱萬円」、2万円の場合は「金弐萬円」といった感じで袋の中央に縦書きで記入します。
また壱を「一」、萬を「万」と記入しても大丈夫です。
中袋に枠線が書かれていて、金額を記入する欄があればその欄に記入しましょう。
縦書きの場合は上と同じように漢数字、横書きの場合はアラビア数字で記入してください。
そして中袋の裏側には、住所・氏名を書く欄があります。
こちらは出産祝いの場合は記入しなくても失礼にはなりません。
ですが中袋の裏面の住所・氏名の欄はもともと、相手の方がお礼状などを書く際に配慮する為のものなので一般的なお祝いの時にはきちんと記入しましょう。
お金の向きにも決まりがある?

あまり意識したことがない方や・よく分からないと悩むのがお金の向きや入れ方ですよね。
基本的に決まりはありませんが、一般的な入れ方はありますので知っていると出産祝いだけでなく結婚の祝儀袋などを使うときに便利です。
お札が複数ある場合には、裏表と上下を揃えてから入れましょう。
肖像画(顔)が上にくるように入れます。
これは袋からお金をだす際に、表の肖像画が先に見えると豪華な印象があるという理由があるからです。
※肖像画が描かれている方が表になるので間違えないように気を付けましょう。
ほとんどの祝いごとは、このお金の向きで失礼にあたることはありませんので是非覚えておきましょう。
ちなみにお札の裏面を表向きに入れてしまうと「顔を伏せるという」意味で、不祝儀袋の扱いになりますのでくれぐれも間違えないようにしましょう。
記入する際に注意することは?
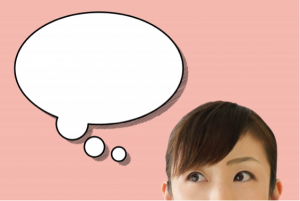
袋の色は基本的に白のものがいいでしょう。
最近はピンク・ブルーなどの袋が販売されていますが、これらを使うときは親しい間柄の友人などがいいです。
金額の記入は上でも言いましたが、漢数字・アラビア数字で記入すること。
そして中袋に記入する物は、表書きつまり祝儀袋と同じ物で記入します。
筆ペン・サインペン・万年筆がいいでしょう。
ただし中袋の記入欄が小さい時には、ボールペンなどの細いもので記入して大丈夫です。
私自身は見たことないですが、知人の話では最近ではPC・ワープロで印刷する方もいると聞きました。
これは現代らしいですが大変失礼にあたるのでしないでください。
そして祝儀袋を選ぶ際には、水引きの結び方の種類に気を付けましょう。
出産祝いの時は蝶結びになっている袋を選びます。
なぜなら蝶々結びは何度解けても結ぶことができるということから、「何度繰り返しても嬉しいこと」という意味を表すからです。
逆に避けたい水引きは
結び切り
結び切りには「二度とおきないでほしい」といった意味が込められています。葬式などに使われますので避けましょう。
「寿」の表書き
意外と知られていないのが、表書きが「寿」を使っている袋を使うこと。と画数が偶数になり縁起が悪いので避けた方がいいでしょう。
水引が印刷のもの
こちらは金額が少ないときに使うのがマナーです。
金額が高額な時に使うのは向いていないので避けましょう。
祝儀袋の相場は?
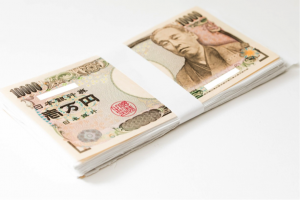
祝儀袋の相場については贈る金額で変わってきます。
貰った相手が恐縮・負担に感じないように豪華さと袋の格のバランスを意識して選びましょう。
- 5,000~10,000円包む場合=200~400円
- 10,000~30,000円の場合=300~600円
- 30,000~50,000円の場合=600~2,000円
- 30,000円以上の場合=1,000~2,500円
の袋になります。
これらを参考に祝儀袋を選んでください。
最後に

大げさかもしれませんが、これらのマナーが出来ていなければ自身の親や身内の方も出来ていないと思われる方もいらっしゃいます。
特にご年配の方に多いです。
そう思われない為にも、贈った相手の方がご家族で同居している場合は尚更きちんと確認をして渡した方が安心です。
これらのマナーを知っていると役にたつ場面が多々ありますので、一度しっかりと覚えておきたいところですね。























